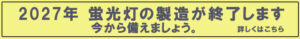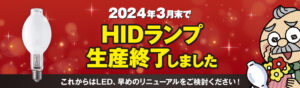大阪府庁本館(大阪市中央区)で1月12日に発生した火災は、停電時に点灯する非常用照明の間違った使い方が原因だった可能性が浮上し、
府警による詳しい調査が続いている。
非常用照明は、火災や地震などで停電が起きた際に避難者を誘導するため、一定規模の建物で設置が義務付けられている。
取り扱いを間違えれば二次災害を招く恐れもあり、府が対応に追われている。
「非常用照明の説明書通りになっていなかったことが、一番の問題だったと思っている」
吉村洋文知事は火災発生翌日の13日に現場を視察した後、出火の経緯についてこう指摘した。
火災は12日、府庁本館地下1階の部屋で起きた。同日午後0時15分ごろ、館内の警備室で火災報知機が鳴り、警備員が地下1階の倉庫近くで白煙を確認。
警備員らが初期消火を試みたが消し止められず119番し、駆け付けた消防隊が約3時間後に消し止めた。けが人はなかった。
府によると、火災のあった部屋は広さ約70平方メートルで薬務課が倉庫として活用。出火当時は出入り口が施錠されていた。室内には棚があり、
その上に置かれた段ボールや書類などが激しく燃え、天井側には非常用照明があったという。
館内では日曜日だった同日朝から電機設備の点検が行われ、作業のため火災発覚の約2時間前から停電させており、非常用照明が点灯していた。
照明に近付き過ぎていた段ボールが熱を持ち、発火した可能性がある。
建築基準法では、不特定多数の人が利用したり、一定以上の広さがあったりする建物では、居室や通路などに非常用照明を設置するよう規定。
おおむね6カ月から1年の間隔で、床面を一定以上の明るさで照らせているかなどを点検し、特定行政庁に報告することが義務付けられている。
ハロゲン電球非常照明器具は器具から70センチ以上離すこと!
府庁本館の非常用照明は、平成28年に完了した耐震改修工事で約720カ所に設置。点灯時に高熱を持つハロゲン電球が使われ、説明書では他の物から約70センチ以上離すよう警告されていた。
火災は12日、府庁本館地下1階の部屋で起きた。同日午後0時15分ごろ、館内の警備室で火災報知機が鳴り、警備員が地下1階の倉庫近くで白煙を確認。
警備員らが初期消火を試みたが消し止められず119番し、駆け付けた消防隊が約3時間後に消し止めた。けが人はなかった。
府によると、火災のあった部屋は広さ約70平方メートルで薬務課が倉庫として活用。出火当時は出入り口が施錠されていた。室内には棚があり、その上に置かれた段ボールや書類などが激しく燃え、天井側には非常用照明があったという。
館内では日曜日だった同日朝から電機設備の点検が行われ、作業のため火災発覚の約2時間前から停電させており、非常用照明が点灯していた。照明に近付き過ぎていた段ボールが熱を持ち、発火した可能性がある。
建築基準法では、不特定多数の人が利用したり、一定以上の広さがあったりする建物では、居室や通路などに非常用照明を設置するよう規定。
おおむね6カ月から1年の間隔で、床面を一定以上の明るさで照らせているかなどを点検し、特定行政庁に報告することが義務付けられている。
府庁本館の非常用照明は、平成28年に完了した耐震改修工事で約720カ所に設置。点灯時に高熱を持つハロゲン電球が使われ、説明書では他の物から約70センチ以上離すよう警告されていた。
出典:毎日新聞 、産経ニュース